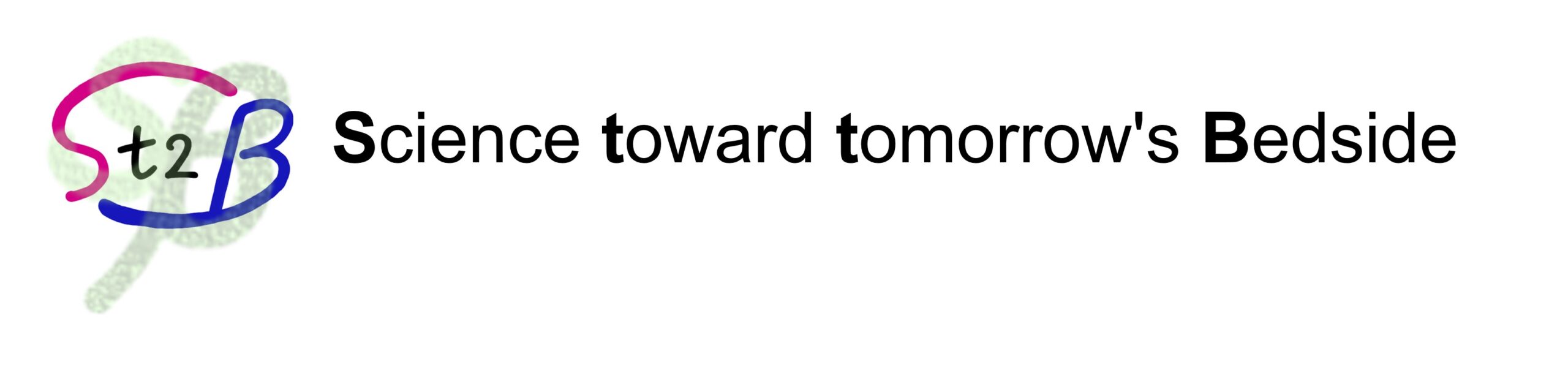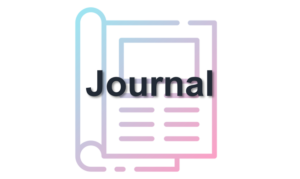周術期治療と高齢化の波
最近は欧米でも肺癌患者の高齢化が進んでいるが、とりわけ日本とイタリアは一昔前から高齢化著しい国の代表になっている(と聞いた)。肺癌診療ガイドラインではNSCLCにおいて75歳以上を高齢者と定義しているが、2017年度のがん登録・統計を見ると日本は約半数の肺がん罹患者が75歳以上を占めている。
そのような状況にもかかわらず、NSCLCの臨床試験データでは相変わらず65歳をカットオフとしたサブ解析データが主流となっており、日本の高齢者の定義である75歳をカットオフとしたサブ解析データはほとんど見当たらない。一方で最近注目されているような分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤に関しては、少なくとも進行期/転移性NSCLCの高齢患者には効果が乏しいエビデンスも少なく、臨床試験データからも(これも上述のとおり65歳をカットオフにしている時点でエビデンス的に疑問なのだが)年齢に関係なく有効性が認められることが示唆されているため、最近はあまり高齢者の定義は言われなくなりつつあると感じる。
しかしながら、今後は周術期治療にもTKIやICIが承認される時代に突入し、改めて手術適応かどうかを含めて高齢者に対するこれら治療介入の是非が議論になってくると予想される。ガイドラインはあくまで患者の年齢を含む身体的機能で判断される治療アルゴリズムの推奨だが、そこには当然ながら患者や家族の希望(考え方や価値観)、社会的状況(就労ステータスや金銭的余裕など)などは考慮されていない。患者本人の治療理解を含めた認知機能の問題、家族など周りのサポートが得られるかどうか、金銭的な問題(国の医療財政はもちろん、患者個々人の毎月の医療費負担も)、通院手段など、これまでの進行期治療と同様とりわけ高齢患者では治療方針の決定において問題になると思われる。
進行期治療では内科医が中心となって決められていた治療方針も、周術期治療では外科や放射線科など複数のチームによる集学的な議論と治療方針の決定が重要となる。周術期治療が対象となる患者では高い確率で根治が望めるため、薬物療法による手術不能や副作用といったリスクを最大限回避しつつ、over-treatment(過剰な治療)やunder-treatment(過小治療)とならぬよう、個々人の患者にbest-treatmentが行き届いてほしいと願っている。