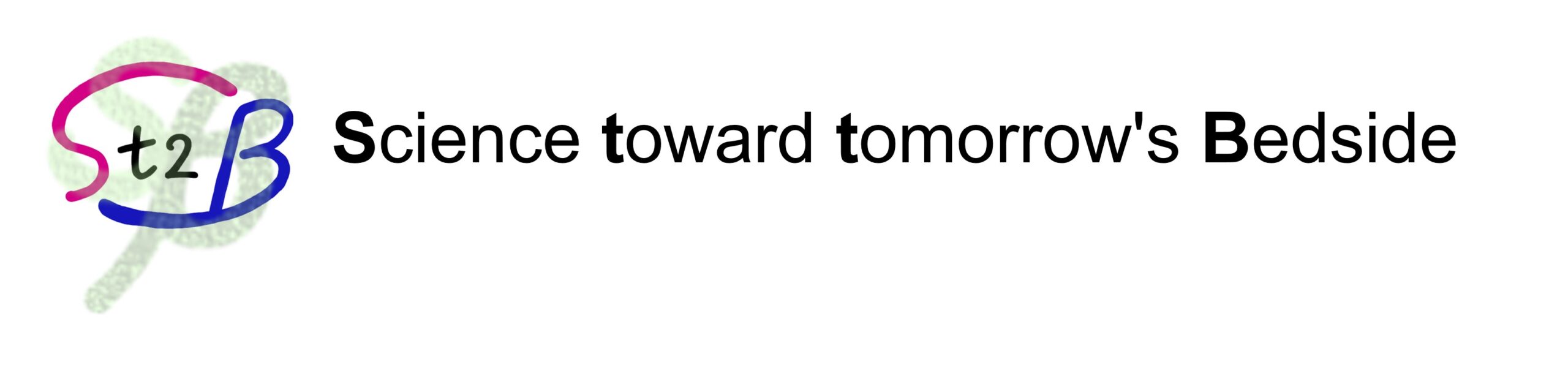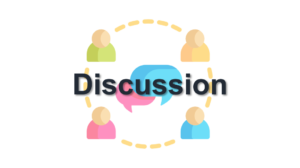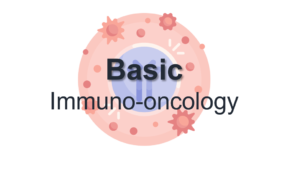なぜ分子標的薬は腫瘍細胞を根絶できないのか?
分子標的薬は高い腫瘍縮小効果を持つにも関わらず、ほぼ全ての症例でいつかは必ず再発するという欠点を持つ。一方、ここ数年で急速に開発が進んだ免疫チェックポイント阻害剤 (ICI)は、がんの種類に関わらずある一定の割合で根治を実現させてきた。この違いはどこから来るのだろうか、その理由について分子標的薬の耐性機序に着目して考えてみたい。
手強い耐性株
分子標的薬に対する抵抗性には、1)治療により薬剤感受性細胞が除去されるとともに、既存の微量な非感受性細 胞集団が増殖していくこと(初期耐性)、2)治療への長期暴露によりde novoの耐性変化が現れること(獲得耐性)の二種類が挙げられる。初期耐性は早期脱落によりORRやPFSの成績悪化につながる因子であり、獲得耐 性は効果の持続を左右する因子と考えられる。すなわち、一度は完全に腫瘍を制御できたかに見える奏効症例でも最終的には抵抗性となる、この獲得耐性メカニズムこそが、分子標的薬の根治を妨げている要因である。
この現象を説明する一つの概念として、drug tolerant cell (DTC)が挙げられる。これは、薬剤によるストレス によって一時的に存在する増殖能の低い細胞の亜集団であり、特定のシグナル伝達経路の再活性化、エピジェネティックまたは代謝の再プログラミング、アポトーシスの抑制、転写リモデリングなど様々な因子の関与が示唆されている。これらの複雑な腫瘍細胞の変化により、細胞の長期的な生存が維持され、より安定した不均一な耐性メカニズムの獲得を誘導していると考えられている。(Leonce et al. Mol Cancer Res. 2022 、Marusyk et al. Cancer Cell. 2020) DTCは化学療法や分子標的薬で広く研究が進んでいる一方、ICI治療過程では報告がなく、DTCの制御こそが根治に近づく一つの鍵であると考えられる。
薬の切れ目が効果の切れ目
ICIの特徴の一つに、薬剤を中止しても一部の症例において効果が長く持続することが挙げられる。このdurale responseは、自己の免疫を活性化することで間接的に腫瘍への攻撃性を維持するICIの強みであり、根治可能性 を高める結果につながっている。 一方分子標的薬は、止めると再増悪する薬剤と従来から考えられており、前述のDTCがその一つの原因と考えら れる。腫瘍が根絶されたのように見える耐性獲得前の状態であっても、一時的にわずかに存在するDTCが生存を 維持しており、薬剤中止とともに薬剤感受性と増殖能力を回復させる。(Mikubo et al. J Thorac Oncol. 2021)つまり分子標的薬の場合、CRが得られたとしても油断はできないのである。
益々重要性が高まる根治という概念
予後の延長が治療目的である進行期においては、根治の可否に関わらず分子標的薬の効果は高く評価されてきた。しかしながら、周術期における薬物療法が注目され始めた今、いかに手術後の再発を抑えることができるかという点が重要視されるようになり、根治可能性が薬剤の評価項目になると考えられる。術後再発のメカニズムにDTCの概念が当てはまるかどうかは現時点では不明であるが、周術期における分子標的薬の使用により再発を遅らせることはできても、最終的にはDTCが再発の原因を作っている可能性は十分考えられるのではないか。
敵を腫瘍固有の分子に絞り込むことで、正常細胞が攻撃対象から外れ毒性回避に繋がるメリットがえられた一方で、少し変化した敵をも見逃してしまうことになりかねない。これは特定の分子をピンポイントで標的とすることの限界かもしれない。
今後様々な耐性メカニズムの解析やそれに伴う併用療法の開発が進み、更なる長期生存が実現することに期待したい。(Leonce et al. Mol Cancer Res. 2022 )
=分子標的薬とDNA損傷修復機構=
分子標的薬の再発メカニズムの解析や耐性を遅らせるための併用薬の検討は現在までにも複数報告がある。
最新の報告としては、分子標的薬がDNA二本鎖切断(DSB)を誘導し、それに伴ってDSB修復プロセスが活性化(特にATM分子の発現が上昇)することで細胞死を逃れ生存が保たれていることが明らかになった。実際xenograftモデルにおいて、EGFR-TKIとATM阻害剤の併用により、腫瘍の増殖を長期にわたり強く抑えることをが示されている。既に分子標的薬抵抗性のメカニズムとしてATM発現が上昇していること、ATM遺伝子欠損腫瘍では分子標的薬に対する抵抗性獲得が遅いことなどが、ヒトでも確認されており、今後の併用薬の効果の検討が待たれる。(Ali et al. Sci Transl Med. 2022)