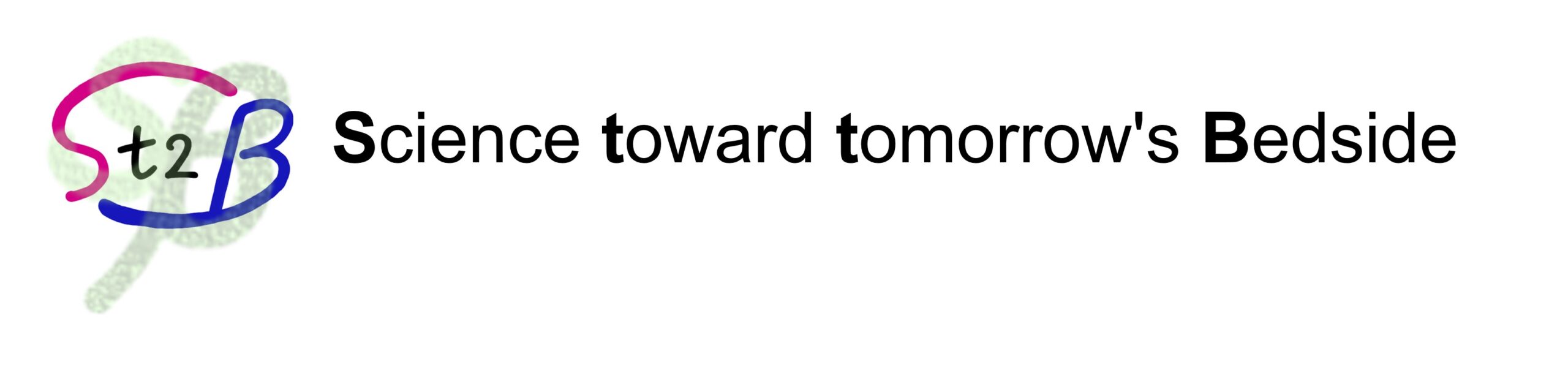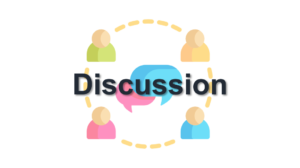肺がんのネオアジュバント療法としての免疫チェックポイント阻害剤+化学療法の実施に賛成?反対?
従来の化学療法(chemo)のエビデンスでは、術前(ネオアジュバント)、術後(アジュバント)の成績はほぼ同等であり、ともに手術単独と比べてOSで5%程度の改善が期待できる(NSCLC Meta-analysis Collaborative Group Lancet 2010, Lancet 2014)。
一方、ICIでは少なくとも前臨床のデータや作用機序の観点から、術前ICIがより有望視されている。
臨床ではNivo+chemo (CheckMate-816)の病理学的評価の結果に注目が集まっているが、果たして実臨床で積極的に使われる日は近いのか?ここでは賛成派と反対派の両観点から考えてみる。
[賛成派]
CheckMate-816の結果を受け、ネオアジュバント療法としてのICI+chemoの併用がFDAにて承認された。申請からわずか4日という超迅速な承認であったことからも、この治療法への期待が窺われる。
そこでまず、ネオアジュバント療法としてのICIレジメンに賛成の立場で、メリットを考えてみる。
1、有効性を裏付ける科学的根拠が充実
ICIのメカニズムを考えると、T細胞のプライミング・腫瘍特異的T細胞クローンの拡大に繋がる腫瘍抗原がより多く存在する術前に投与することで、より有効性を発揮すると考えられる。(詳細はこちらの記事参照。)前臨床データだけでなく臨床においても、メラノーマのOpACIN試験において、ネオアジュバントの(安全性はともかく…)有効性が示されている。(Blank et al. Nature Medicine 2018)
また抗原刺激の持続により、T細胞の分化が疲弊状態へと進んでいくが、疲弊初期状態は可逆的であり、ICIにより再活性化可能と考えられている。一方抗原刺激の慢性化により疲弊状態が続くと、T細胞上の疲弊マーカー発現パターンが変わり、疲弊状態はもはや不可逆となる。(この時のT細胞上の特徴的な疲弊マーカー発現パターンはEpigenetic Scarsとも言われている。 Abdel-Hakeem et al. Nat. Immunol. 2021)このことは、T細胞ができるだけ疲弊初期にいる段階で、即ちできるだけ早期の腫瘍においてICIを導入する根拠となるのではないか。
2、少ない患者負担で大きなベネフィット?
アジュバント療法は、目には見えない腫瘍をターゲットとし、AEのリスクも負いながら、高価な治療を継続する必要がある。一方ネオアジュバント療法に関しては、目に見える腫瘍をターゲットに比較的短い期間(3-4サイクル)で治療が完了し、画像や外科的切除時の病理学的奏効、術後のMRDなど、より多面的に評価可能であるため、不要な治療を減らし、リスクやコストの面でもネオアジュバント療法のメリットは大きい。
ネオアジュバント療法の一つの大きな懸念点としては、手術への影響が挙げられるが、ICI単剤のネオアジュバント療法の安全性に関しては、これまでにも既に複数の治験において確かめられている。また術前のICI+chemoに関しても、CheckMate-816試験の結果を見る限り、AEや手術の遅れに繋がるリスクは殆どないことが見て取れる。それどころかむしろ、ICI+chemotherapy治療を実施することで、より低侵襲性の術式の割合が増え、手術時間の短縮や出血量の減少につながり、術後の転機が良好であったと報告されている。(Spicer et al. JCO 2021)
3、OS延長への期待
周術期の治療目的はなんといっても治癒である。そのため、pCR率を上げることができたとしても、最終的な再発率・長期生存確率のデータが重要だと考えるのは当然である。現時点のところ、ネオアジュバント療法による病理学的奏効率と生存期間との相関が明確に示されているのはchemoのみであり、ICI+chemoにおける評価は、現在進行中のPhase3試験の中で解析が進むと予想される。しかしICIのメカニズムを考えると、遠隔転移のリスク要因である微小転移病変に対する持続的な免疫監視効果が期待できるため、ICI+chemoによる病理学的奏効がその後の長期生存につながる可能性は、十分考えられるのではないか。
以上の理由から、ICI+chemo療法はICIの作用メカニズムから考えても、術前で大きなメリットが得られると考えられる。FDAでの承認を受け、今後更に注目される治療法になるのではないか。
とはいえ…
ここまで賛成派として意見してきたが、エビデンスの数や追跡期間から考えても結論を出すには時期尚早であることに疑いの余地はない。また、最もベネフィットの高い症例を選択する指標がないこと、更にはドライバー変異症例に対するエビデンスが無いことなど、課題は多く残されている。
そこで次に、術前ICI+chemoの抱える問題点を中心に考えていきたい。
[反対派]
ネオアジュバントchemoのみのMPR/pCR(それぞれ20%、5%;Hellmann MD et al. Lancet Oncol 2014)に比べて、ICI + chemoにおけるMPR/pCR(それぞれ37-83%/18-63%;Forde PM et al. Abst#CT003 @ AACR 2021, Provencio M et al. Lancet Oncol 2020, Shu CA et al. Lancet Oncol 2020, Rothschild SI et al. JCO 2021)は非常に有望ではある一方、これら病理学的エンドポイントがOS改善につながるかどうかは現時点で不明である。
唯一、NADIM試験(IIIA期N2 or T4N0/N1症例を対象としたNivo+chemo単アーム Phase 2試験)のみOSデータが得られている(MPR/pCR = 83%/63%、2年DFS = 88.4%/96%、2年OS = 両群とも100%;Provencio M et al. Lancet Oncol 2020)が、CheckMate-816試験ではNADIMのような有望な病理学的データを反映しておらず、ネオアジュバントICI+chemoを実臨床でSoCとする前に、以下の幾つかの懸念を解消する必要があると思われる。
1. 病理学的評価は承認に十分な指標か?
DFSはICI登場前から周術期治療レジメン承認のエンドポイントして許容されているが、MPR/pCRは承認のためのエンドポイントとしてコンセンサスが得られていない。そもそもMPRはネオアジュバントchemoにおけるOSのサロゲートマーカーとして採用された背景があり、chemo単剤より壊死が少なく線維化が多いとされるICI+chemo療法においては、MPRの解釈が困難となる可能性がある。つまりMPRをICIレジメンのエンドポイントとして使用する前に、改めてMPRの定義の標準化が必要である。
また、周術期治療の目的が治癒であることからも、OSが最重要指標であり、臨床試験でも主要評価項目とすべきである。
2. 治療介入が必要な症例を絞り込めるか?
ネオアジュバントchemo施行有無に関しては、「臨床病期」以外の患者選択の基準がないのが現状であり、ICI+chemoに関しても、CheckMate-816の結果を見る限り、腫瘍PD-L1やTMBなどバイオマーカーとしての有望な指標は得られていない。ひとつの解決策としてPD-L1やTMBを含めた「TME signature」を適切に評価することが考えられるが、術前に十分な検体量が得られるとは限らず、更にはTME解析をNGSで実施する場合はTATの問題も無視できない。
また、早期NSCLCにおけるドライバー変異症例に対するICIの有効性エビデンスが存在しておらず、術前の段階で全例に対して遺伝子検査を実施する必要性など、新たな課題が生じ得る。
3.実臨床(Real World)でどこまで現実的な治療オプションか?
周術期ならではの治験のlimitationとして、比較的状態の良い症例が登録されるという一般的な治験の特徴と併せて、手術の技量など地域ギャップが生じる可能性が考えられる。また、CheckMate-816試験では、手術実施率(83% vs 75%)、完全切除率(83% vs 78%)、より低い肺全摘術(pneumonectomy)施行率(17% vs 25%)と、ICI+chemo群の方が優れた成績となったが、最も重要なdown-stagingに関しては報告がない。更に、RCT(治験に登録された比較的状態の良い患者)ですら、~15%の症例で治癒目的の手術が施行できなかったことから、実臨床ではより多くの症例でAEに起因する手術の遅延や手術不能となるリスクが懸念される(これらデータに関しては、標準化された方法によってRCTとRWDの両方で評価されるべき)。
また、至適サイクル数、至適レジメン(ICI単剤 or chemo combo [IIIA期N2は更に+RT?])の明確なコンセンサスがなく、実臨床で使っていくためには、まだまだ多くのデータが不足しているだろう。
以上の理由から、術前ICI+chemo療法が実臨床で標準治療として積極的に使われるレジメンとなるためには、もう少し時間がかかるのではないだろうか。
また、National Cancer Database登録患者35,134人のうち、たった3%(1,154例)が術前chemoを施行しており、大半が手術のみ(53%)、または手術+術後chemo(44%)という現状である(MacLean M et al. Oncotarget 2018)。
国内の状況を見ても、術前治療が対象となる症例に対してchemoのみ(1.4%)またはchemo+RT(1.4%)、術後治療対象症例全体では約30%が手術+術後chemo施行と、周術期治療における薬物療法はほぼ全てが術後アジュバントで行われている状況である(Okami J et al. JTO 2018)。
そのためICI+chemo承認後、どのくらいの治療医が実臨床において「術後 → 術前」薬物療法へマインドチェンジをするかは未知数である。
=なぜ術後アジュバントchemoが主流なのか?=
エビデンスの豊富さ ・臨床病期の情報のみでは本当にchemoが必要かどうか不明(術後の病理病期で追加の補助治療の要否を判断すべき) ・術前治療によるAEや病勢増悪に起因したインオペのリスク回避