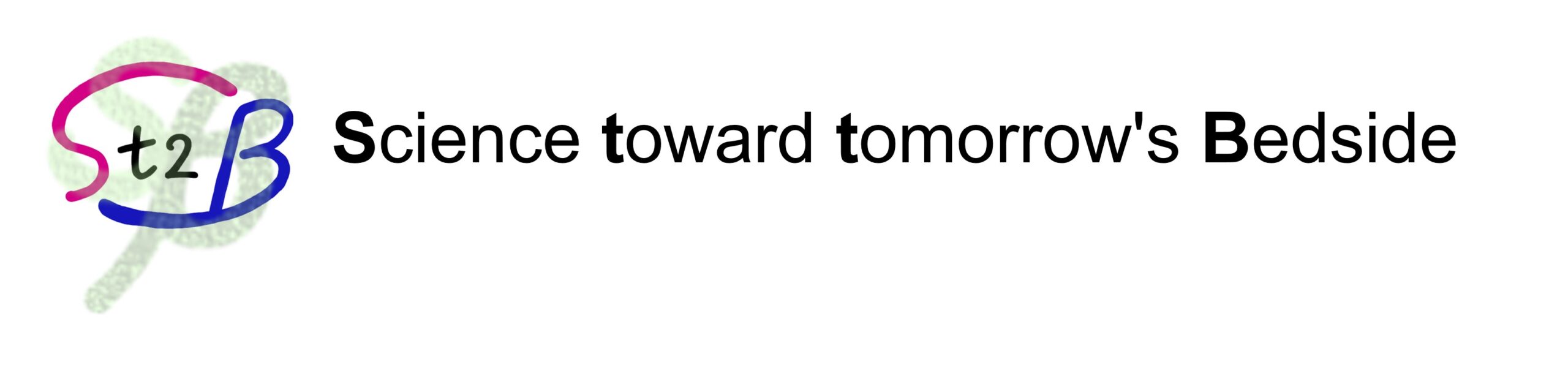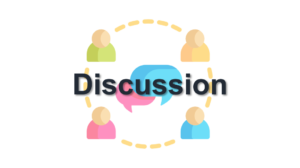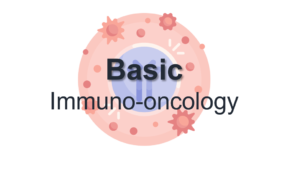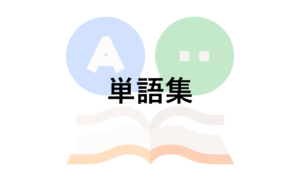術後アジュバントとしての免疫チェックポイント阻害剤のバイオマーカー:腫瘍のPDーL1の意義は?
進行期ICI治療においてひとつのバイオマーカーとなっている腫瘍のPD-L1。術後アジュバントICIが 実臨床で使われる日が近づいている今、改めて腫瘍のPD-L1発現の意義を考えてみたい。(*ここで のICIは、抗PD-1 […]
免疫チェックポイント阻害剤は術後より術前がbetter?:腫瘍ドレナージリンパ節にフォーカス
(その1)で「術前ICI > 術後ICI」の利点として、腫瘍内T細胞クローンの拡大やCD103+ (Batf3+ ) DCの重要性について触れたが、今回は新たな知見を含めてICI投与における腫瘍ドレナージリンパ節( […]
なぜ分子標的薬は腫瘍細胞を根絶できないのか?
分子標的薬は高い腫瘍縮小効果を持つにも関わらず、ほぼ全ての症例でいつかは必ず再発するという欠点を持つ。一方、ここ数年で急速に開発が進んだ免疫チェックポイント阻害剤 (ICI)は、がんの種類に関わらずある一定の割合で根治を […]
進行期EGFR変異陽性肺がんの初回治療はosimertinib一択か?(その2)
FLAURA試験の画期的な結果を受け、現在のEGFR変異症例に対する治療にはosimertinibが最も優先される流れとなっている。確かにそのPFS延長効果や脳転移への有効性を考えると、osimertinibの魅力が大き […]
肺がんのネオアジュバント療法としての免疫チェックポイント阻害剤+化学療法の実施に賛成?反対?
従来の化学療法(chemo)のエビデンスでは、術前(ネオアジュバント)、術後(アジュバント)の成績はほぼ同等であり、ともに手術単独と比べてOSで5%程度の改善が期待できる(NSCLC Meta-analysis Coll […]
肺がん治療におけるリキッドバイオプシーの使いどころは?(その1)
ctDNAの使い方overview early-stage NSCLC根治を目的とした局所治療によりいったん腫瘍が完全になくなったように見えても、ある一定の割合で再発リスクが存在する。目に見えない腫瘍を対象に治療の必要性 […]
進行期EGFR変異陽性肺がんの初回治療はosimertinib一択か?(その1)
FLAURA試験の画期的な結果を受け、現在のEGFR変異症例に対する治療にはosimertinibが最も優先される流れとなっている。確かにそのPFS延長効果や脳転移への有効性を考えると、osimertinibの魅力が大き […]
コンパニオン診断と薬剤の紐づけまとめ(2023/8/1現在)
次々と増えていくドライバー遺伝子と治療薬、これだけでも複雑なのに、遺伝子変異と治療薬を紐づけるコンパニオン診断薬も統一化されていない状況である。ここではそれぞれの診断薬でどの治療薬が使えるのか整理してみた。一つの検査法で […]
三次リンパ構造(Tertiary Lymphoid Structure: TLS)
生後に非リンパ組織に存在する免疫細胞の組織化された構造物(凝集体)である. 生理的な条件下では見られず、炎症を起こした組織で見られ、慢性炎症性疾患や自己免疫疾患、がんに関連している. その形成のきっかけや腫瘍内免疫応答に […]