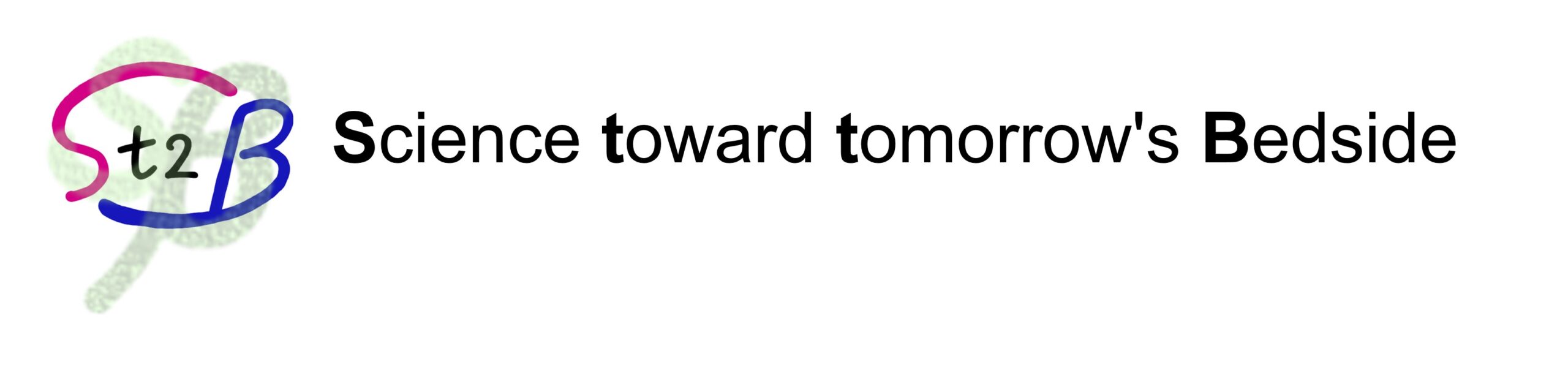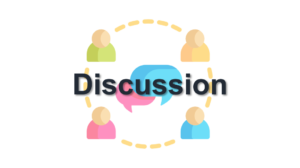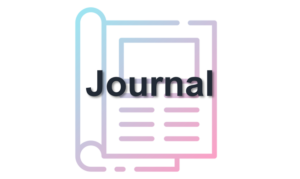いいことばかりではない!?免疫チェックポイント阻害剤と放射線療法の併用
今回は、放射線療法(RT)が腫瘍の転移を促進させる、というNatureからの報告(Piffkó A et al. Nature 2025)から考えたことをまとめてみた。
RTといえば、照射野ではない転移巣の縮小も期待できる、いわゆるAbscopal effectがよく知られている。しかし今回の報告では、RTによってがん細胞からのアンフィレグリン(AREG;EGFRリガンドの一種)の産生を誘導し、それが免疫の抑制(EGFR陽性の骨髄系細胞を免疫抑制性へ再プログラムさせて貪食能を低下させる、等)、ひいては予後不良につながることが示唆されている。
つまり、場合によってはRTによるAbscopal effectがAbscopal ”toxicity”となる懸念もあり、アンフィレグリンが今後のバイオマーカーや治療標的になり得るかもしれないことを示唆している。
そしてここからひとつ踏み込んで考えると、今回の知見は、RTと免疫チェックポイント阻害剤(ICI)との併用療法にも影響すると思われる。
この点に関しては以前の記事で取り上げた通り、照射によってhotな免疫環境を作るというメリットが示唆される一方で、Trex1によるcGAS-STING経路の不活化(Vanpouille-Box C et al. Nat Commun 2017)や免疫細胞へのダメージ(Galluzzi L et al. Nat Rev Clin Oncol 2023)等、デメリットがあることも分かってきている。この後者のデメリットに、今回の知見が新たに加わったと考えることができるだろう。
今後の検討事項としては、アンフィレグリンの作用の継続時間や線量依存性が気になるところである。それによってRTとICIとの併用療法を検討する場合の最適な線量や併用タイミングが分かるかもしれない。
がんの治療法は、従来いわゆる3本柱(手術、放射線療法、薬物療法)で考えられてきたが、薬物療法の開発が進歩するにつれて、併用療法など治療法が煩雑化してきた。
まず早期ステージの場合には、とにかくがんを手術で取り除く局所療法→手術が困難な場合には放射線による局所療法→進行症例には全身療法としての薬物療法、という病期毎の縦割りの治療概念が当てはまらないケースも出てきたことである。手術メインの早期治療にも薬物療法が台頭し、逆に薬物療法の高い治療効果によって進行期でも"サルベージ"手術が検討される時代になってきた。これが、昨今よく耳にする多職種チームによるMDTの重要性につながるわけだが、こちらは過去に何度も取り上げたので詳細は割愛したい。
もうひとつは、薬物療法の多様性が大幅に増したことである。従来3本柱としての薬物療法は、いわゆる細胞障害性抗がん剤(化学療法)を指すことが多かった。しかしその後、分子標的薬やICIが出てきたことで状況が一変した。特にICIは、宿主の免疫機能を回復させることがメインの作用であり、がん細胞を直接標的とする従来の抗がん剤の概念を覆した、といっても過言ではないだろう。
このふたつの変化により、病期毎にキーとなる治療モダリティは何か、それぞれの治療モダリティの意義とは、ということを今一度見直す必要があるだろう。この点からICIとRTとの併用療法を考えると、局所療法としての放射線療法から、ICIの効果増強のための放射線療法として、最適な使用法を見直すべきだろう。