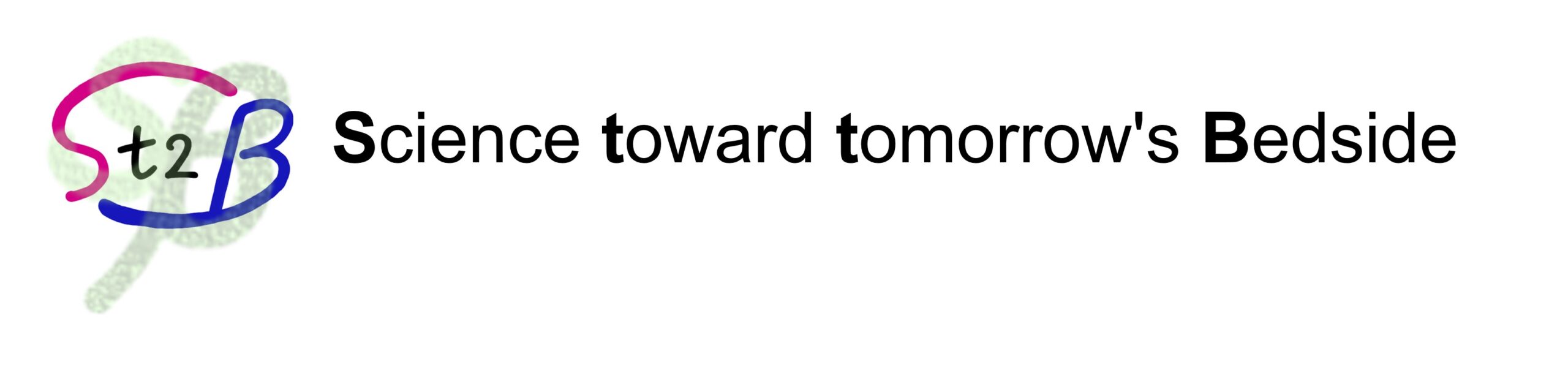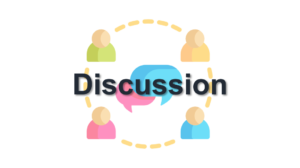肺がん治療におけるリキッドバイオプシーの使いどころは?(その1)
ctDNAの使い方overview
early-stage NSCLC
根治を目的とした局所治療によりいったん腫瘍が完全になくなったように見えても、ある一定の割合で再発リスクが存在する。目に見えない腫瘍を対象に治療の必要性や効果の判断をすることは非常に難しく、ctDNAによるMRDのモニタリングの活躍が期待されている。
手術で取り切った症例全例に、必要かどうかも分からない術後アジュバント治療を実施することには、まだまだ抵抗の声もある。(参考記事:ADAURA, IMpower010)そこで、術後のctDNAが陰性であればいったん治療から解放、そしてctDNAが陽性になった段階で治療介入再開、という治療戦略を検討した前向き試験として、MERMAID-2試験が実施中である。これは術後のNSCLC症例を対象に、最大2年間連続したctDNA分析による追跡調査を行い、ctDNAが陽性となった場合にICI投与群またはプラセボ投与群にランダム割り付けをするデザインになっている。
ただ、 ctDNAによる再発早期発見/早期治療介入は、CT画像による再発発見と比べてどのくらい臨床的意義があるのか、疑問が残るところではないか。 [CRT後] consolidation治療の必要性の判断、治療効果予測
手術不能症例におけるCRT後のconsolidation治療に関しても、AE発現等の懸念から、全例を治療対象とするかどうかについて検討の余地がある。CRT後にctDNA陽性かつICI consolidation後にctNDAレベルの低下が見られた症例では、ICI consolidationの恩恵を受ける。一方、CRT後にもともとctDNA陰性であった症例は、ICI consolidationの実施の有無によらず、低い再発率を保つことができたとの報告がある。CRT後のICI consolidationの必要性の判断、早期の段階での効果判定に有用であることが示唆される。(Moding et al. Nature Cancer 2020)
Metastatic NSCLC
従来のEGFR遺伝子変異検出の検討の経験からか、early stageの場合と比較し、特定の遺伝子変異のみに着目したctDNA解析が進んでいるように感じる。
遺伝子検査に関しては、分子標的薬のコンパニオン診断として、国内でもFoundationOne® Liquid CDx がんゲノムプロファイルが昨年承認されている。海外では既に、liquidで最初に遺伝子検査をし、陰性の場合のみtissueによる再検査を実施する流れができているが、果たして日本では今後どのような検査体制になっていくのだろうか。
また治療効果予測に関しては、分子標的薬治療前後のctDNAの挙動と治療効果の相関を検討した報告を、学会等で見かけることが増えてきた。ただ、ctDNAが消失したからと言って薬剤をやめるというのはなかなかに勇気が必要なことだと思う。逆にctDNAレベルの上昇が分かれば、治療の早期中止の判断につながる可能性はあるが、CT画像検検査以上のメリットがあるのかどうかについては不明である。実臨床での使用はまだまだ検討の余地ありそうだ。 [耐性後] 耐性メカニズム同定
分子標的薬治療に耐性化した症例において、その原因遺伝子変異を、ctDNAを使って解析することが検討されている。ただし偽陰性の懸念や形質転換の可能性の排除のためには、tissueによる検査の実施が好ましい。耐性後のctDNAの解析は、再生検が難しい症例等に限ったオプションとしての位置付けになるのではないか。
ctDNAをめぐる課題
患者さんへの負担を考えると、tissueではなくctDNAが好ましいことは明白である。しかしながら、ctDNAが実臨床で使われるようになるまでには、まだまだ解決すべき課題が山積みである。
下記に思いつく限りの問題点を挙げた。ぜひコメント欄にて皆さんのご意見もいただきたい。
1、tissueによる検査とのconcordnceに関するエビデンスが不十分であること
2、偽陰性回避ために非常に高い感度が求められること(MRDのモニタリング等、非常に微量な腫瘍を対象とするケースも多いため、カットオフ値の設定も課題となるだろう。)
3、偽陽性の懸念も?(2と矛盾するようであるが、感度を上げることにより、必ずしも治療介入が必要なレベルの腫瘍由来ではないシグナルも拾う可能性が出てくる。また、腫瘍に由来する変異と、CHIP(=clonal haematopoiesis of indeterminate potential)により加齢に伴って自然に蓄積した体細胞変異との区別も課題である。)
4、検査の最適なタイミングが不明であること*
5、コストがかかること(特に個別化プロファイルによりctDNAの平均遺伝子変異頻度をモニタリングする場合、tissue由来の患者固有のアッセイパネルを作成する必要がある。ただし今はtissueの解析がいらない検査方法も出てきているようであるが…Chen et al. Molecular Diagnosis & Therapy 2021)
6、経時的な複数回のモニタリング検査は、現状の保険償還システムでは不可能であること
*治療によるctDNAの挙動
治療薬開始後の効果とctDNAとの相関に関しては、治療の効果が出ていればctDNAレベルが低下し、期待通りの効果が出なければctDNAレベルが上がる、という単純なものではなさそうである。
たとえば、治療開始直後(=腫瘍が壊れた直後)はctDNAレベルが高いとの結果が報告されている。(Breadner et al. Lung Cancer 2022)そのため、治療効果判定目的のためのctDNAの解析のタイミングには注意が必要である。一方で、治療による腫瘍崩壊によって治療直後は遺伝子変異検出率も上がるとの結果がでているため、遺伝子変異検出目的の場合には、むしろ治療直後のctDNA解析が適しているのかもしれない。