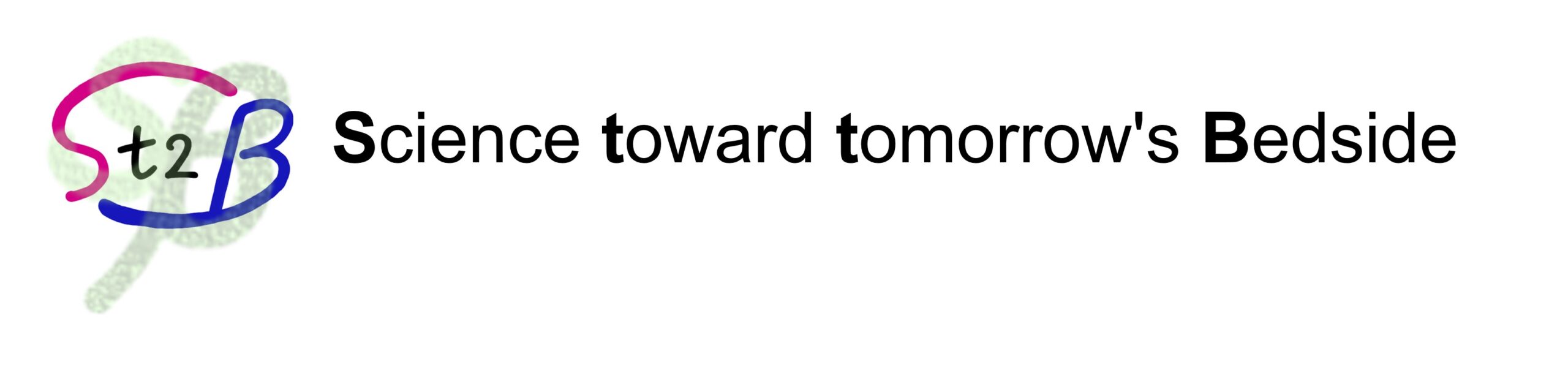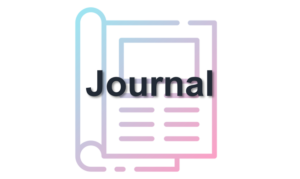メカニズムから考えるTKIとACDの使い分け:HER2変異陽性非小細胞肺がんを例に
2025年8月8日、Zongertinib(HER2-TKI)がHER2変異陽性非小細胞肺がん(NSCLC)の治療薬としてFDAに承認された。HER2を標的とした治療はADCが先行していたが、いよいよTKIの実臨床への導入に期待が高まるニュースだ。
せっかくなので、ここで非小細胞はいがんのHER2標的薬の使い方について少し踏み込んで考えてみたい。
まずZongertinibだが、最近ではAACR 2025にて、既治療のHER2変異陽性NSCLCに対するZongertinibの有効性を検討したBeamion LUNG-1試験のデータが報告された(Heymach JV et al. NEJM 2025)。
既にHER2変異NSCLCに対しては2L治療としてADCのT-Dxd(エンハーツ)が承認されているが、投与法や有害事象の観点から考えると、TKIであるZongertinibに軍配があがるだろう。現在はHER2変異NSCLCに対する1次治療として、Pembolizumab+chemoとの比較試験(Beamion LUNG-2試験)が実施中であり、将来Zongertinibが1LのSoCを塗り替える可能性が高いと予想される。
さてそうなると気になるのは、ADCとTKIをどう使い分けていくか、というCQだ。
まず作用機序を考えると、ADCは標的抗原への結合を介して細胞内に入り込み、最終的にがん細胞をchemo(payload)の力で破壊するが、TKIは標的となるチロシンキナーゼに依存したシグナル伝達を遮断することが主となる(ADCはその他にも、ADCCやADCPを介して抗腫瘍効果を発揮するとの報告もあるが、今回は細かなメカニズムは割愛したい)。
つまり、両者は作用メカニズムの点で決定的な違いがあるため、今後ADCがTKIに取って代わられることはない、つまり両者はそれぞれにメリットがある治療薬と言えそうだ。
となると次に気になるのは、どちらを先に使うのか、というシークエンスの議論になる。
ここで耐性メカニズムに注目すると、ADCでは、抗体に依存したもの(標的抗原の欠損やADCの内在化メカニズムの異常など)と、ペイロードに依存したもの(ペイロード標的の変化や他のシグナル伝達経路の活性化、ペイロードの排出の促進など)が挙げられる(Chang HL et al. J Clin Invest 2023)。一方のTKIでは、on target効果による標的シグナル伝達の再活性化と、off target効果(例:bypass経路や形質転換の出現など)といった標的とは全く別のメカニズムの獲得が挙げられる。
これを念頭において、まずは①ADC→TKIの使用順を考えてみる。上記のADCの耐性メカニズムを考えると、必ずしもADC耐性後に、標的抗原に依存したシグナル伝達経路が活性化しているとは言えない。それどころか、標的抗原が欠損した場合には、TKIの結合相手がいるかどうかも不明だ。実際、HER2陽性乳がんに対するT-Dxdでは、耐性後に約半数でHER2発現の減少が見られ、更にそのうち半数は完全に消失していたとの報告もある(Gouda MA et al. Clin Cancer Res 2025)。このことから、ADC耐性後にTKIを実施しても、必ずしも効果が期待できるとは限らないだろう。
ただし、今回のBeamion LUNG-1試験では、T-Dxd既治療症例に対する効果も検討されており、ORRは48%(ただし、未治療例に対するORR=71%より低い)と、意外にも奏効例が存在する印象を持つ。T-Dxd既治療症例の詳細(特にADC中止理由が初期耐性なのか獲得耐性なのか、それとも安全性なのか…)や、2次治療としてのTKIの効果の持続性といったデータも今後注目すべきポイントと言える。
続いて➁TKI→ADCの使用順を考えてみる。前述の作用メカニズムや耐性メカニズムを考えると、TKIのon/off target効果に関わらず、標的抗原が腫瘍細胞に発現してさえいれば、ADCの効果はある程度期待できると思われる。つまり、①と➁のどちらかと言えば、冒頭にも記載のとおり初期レスポンスや副作用の観点からも➁の使用順に軍配が挙がるだろう。ただし、これに関しては臨床データがないため、Beamion LUNG-2試験では、後治療としてのADCの効果もぜひ評価、検討してほしいところである。