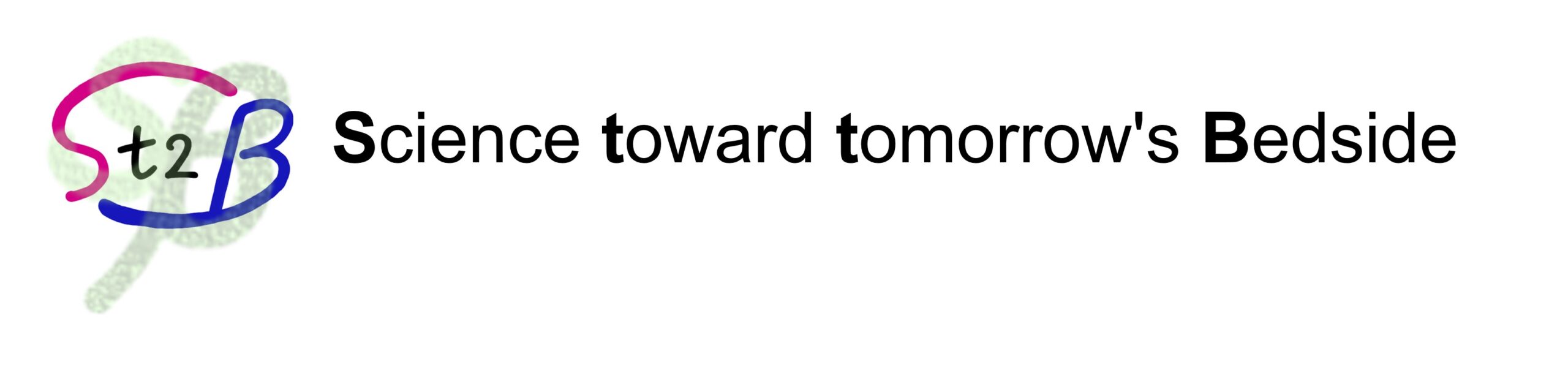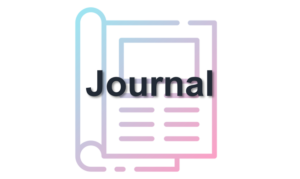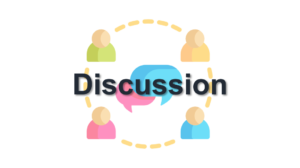非小細胞肺がんのIII期N3症例に対して、切除の可能性に期待した術前療法の実施の意義はある?
非小細胞肺がんの術前治療としてのICIの使用が注目され始めてから今日まで、切除可否の判断が難しいいわゆるborderline resectableに対する治療選択が議論となっている(過去記事参照:https://st2b.net/20250202pm/)。III期に関しては腫瘍の大きさに加え、N2リンパ節転移の個数や大きさ、浸潤度合いが基準となっている。一方で、(適応外ではあるものの)N3のような通常は切除不能と判断される症例に対して術前ICIを実施することで、ダウンステージした場合の切除可能性に期待する声もある。
このような背景の中、(一般的には切除が難しいとされている)T4 and/or N3症例を含むIII期NSCLCに対する術前ICI(抗PD-(L)1薬)+chemoの効果を検討した後ろ向き解析の結果が米国の研究グループから報告された(Ricciuti B et al. JAMA Oncol 2025)。
結論としては、今回対象となったいわゆる手術が難しいとされる症例に対しても、術前ICI +chemoによる高い病理学的奏効が達成され、特にN3症例に関しては(手術できた症例だけで見ると)全例でダウンステージを達成した。
一方、既報の臨床試験の結果と同等以上となる25%(n=28/112)が手術不能となっている点も無視できない。
当該症例に対して術前ICI+chemoが将来的に有望な選択肢の一つとなり得ることは間違いないが、今後は実臨床や前向き試験等で、もう少し詳細かつ慎重な検討が必要だろう。
さて、ここからは同試験で個人的に気になる点を書いていきたい。
まず、術前ICI +chemoの効果予測因子としてしばしば話題になるPD-L1に関してだが、今回は手術の可否に影響していないようだ。もちろんpCR率を見ると、PD-L1発現率との相関は認められていることから、PD-L1は一つの効果予測の指標にはなり得るが、PD-L1だけで治療選択を決めるのは早計と言えるだろう。一方で、臨床病期に関しては、手術の可否との関連が示唆される。特にN3に関しては、よくよく見ると、全体の9.8%の対象症例のうち手術まで辿り着いた症例は4.8%ということだ。つまり今回の研究から、手術が難しいとされるIII期N3やT4の症例に対しても、術前ICI +chemoの効果が一定の割合で期待できる反面、やはり病期が進むほど手術への到達率も低くなるリスクが伴うと言えるだろう。
もう一つ、手術不可となった理由が気になるところだ。RECIST評価と病理評価との相関データを見ると、概してRECIST評価よりも病理評価の成績が良好(RECIST評価でCRが得られていない症例でもpCR達成症例が認められる)だ。これはあくまで手術ができた症例のみのデータだが、もしかしたら、RECIST評価でPD判定となり手術不能と判断された症例であっても、実は手術をしてみた結果viable tumor cellは殆ど認められない、という可能性もあるだろう。ここはPET/CT評価との相関など、今後の研究に期待したい。
以上より、術前ICI +chemoの効果を予測できるバイオマーカー、および手術前に正確な効果を知る評価基準が現時点では十分では無いことが分かるだろう。現在III期N3症例に関しては、前向きNEO SURGE試験(NCT06449313)が進行中である。今後どのような症例に術前ICI +chemoが適しているか、具体的な患者像が同定されることに期待したい。