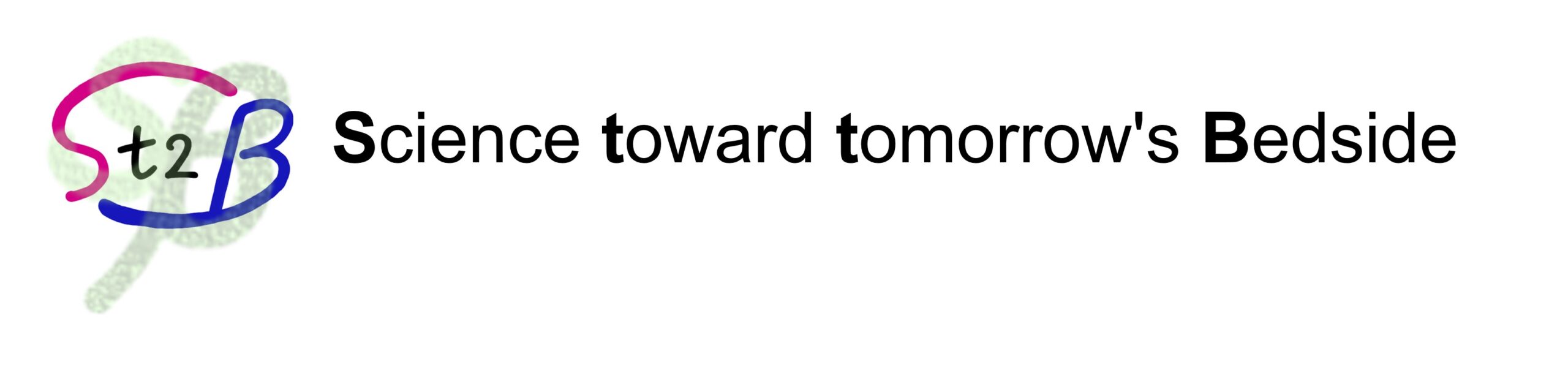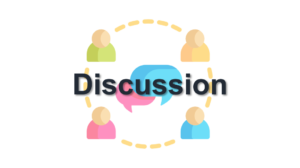休眠細胞の目覚め:ウイルス感染とがんの再発の驚くべき関連が明らかに!
がん治療にとって、初回治療でいかに寛解に近い状態に持ち込めるか、と同時に、いかに再発を抑えるか、ということが完治(cure)の観点において重要なカギとなる。
この再発を抑えるための昨今の研究の方向性としては、大きく分けて以下の2つが重要だろう。
- 微小残存病変(MRD)の根絶:全身に散らばっている目には見えないがん細胞を対象に、例えばctDNAによるモニタリングおよび早期からの(=molecular PDの時点での)全身療法介入の意義などが研究されている
- 休眠細胞(DCCs:Dormant Cancer Cells)活性化の抑制:増殖を止め、薬剤への感受性も失った不活性化状態にあるがん細胞を、目覚めさせることなく根絶(もしくは最低でも休眠維持)することが必要であり、DCCsの特徴やそこを狙った治療開発が進んでいる
今回は➁に関連して、身近なウイルス感染がDCCsを目覚めさせることを明らかにした、非常に興味深い論文(Chia SB et al. Nature 2025)を取り上げながら、DCCsへの理解を深めたい。
同論文では主に乳がんの肺における晩期再発(肺内のDCCsの再活性化が原因と考えられている)に焦点を当てている。まず端的に結論を言うと、インフルエンザやSARS-CoV-2といったウイルスへの感染により産生される炎症性サイトカイン(特にIL-6)が、DCCsを一気に増殖モードに切り替えて再発をきたしてしまう、ということだ。
特に興味深いのは、一度起こされたDCCsは、体内のIL-6レベルが低下した後も、高い増殖能を維持し続けていた点である。具体的には、ウイルス感染によって肺内に形成された特殊な免疫構造である誘導性気管支関連リンパ組織(iBALT)に存在するCD4+T細胞が、抗腫瘍効果を発揮するCD8+T細胞を抑制し、DCCsが生存できる微小環境を作り出していることが明らかになった。通常であれば、抗腫瘍免疫に必須の働きを持つCD4+T細胞が、がん細胞の手助けをする、まさにがん細胞が免疫システムをハイジャックしているようだ。
そして今回の研究は基礎的な解析に留まらず、実際にウイルス感染歴のあるがん患者において、がん関連死亡率や乳がんの肺転移リスクが増加することを明らかにしている。そして、ウイルス感染の際に使われる治療薬のがん治療への応用にも言及されている。今後は、最適な治療薬の検討、そしてウイルス感染とがんの転移の両方を制御できる投与タイミング等の検討も必要になってくるだろう。
さて、最後に今回のデータから更に深堀りしたい点を挙げる。
✓今回の結果は、肺転移以外にも当てはまるのか?
→例えば研究対象になっている乳がんでは、しばしば肝転移なども問題となる。ウイルス感染による炎症が転移を促進する、というメカニズムは、今回着目された肺転移以外にも応用できるのだろうか。転移部位における腫瘍がん微小環境の違いを含め、適切な併用薬が異なる可能性も考えられる。
✓乳がん以外のがん種にも一般化できる減少なのか?
→今回は、晩期再発が問題となる乳がんが主な研究対象であるが、その他のがんにおいても、同様のDCCsの活性化による転移促進メカニズムが成立しているのか、ぜひ研究が進んでほしい課題である。
今回の知見から、これまで知られていなかった身近なウイルス感染とがんの再発との関連性が明らかになることで、DCCsによるがんの晩期再発メカニズムの一端の研究が一気に加速したと言える。これをもとに、今後がんサバイバーにとっての革新的な戦略開発への道が拓かれていくことに期待したい。
細胞傷害性抗がん剤(chemo)がDCCsを覚醒させて再発の原因に?!
Chemoは活発に増殖する(がん)細胞を標的として抗腫瘍効果を得る目的で、進行期から周術期まで広く処方されている。一方、播種性の腫瘍細胞(DTC: Disseminated Tumor Cell)はchemoで完全に除去されず、治療後の再発要因となっていることが最近報告されている(He D et al. Cancer Cell 2025)。
Chemoは特に非腫瘍細胞に作用することによって様々な副作用を引き起こす。本報告では、線維芽細胞の老化を誘導し、さらにSASP(細胞老化随伴分泌現象)や慢性炎症を引き起こして好中球のNET(好中球細胞外トラップ)を誘導する。このNETが最終的に腫瘍微小環境を変化させ、休眠状態にあったDTC(≒DCCs)を覚醒し、転移や再発の促進を引き起こすようである。