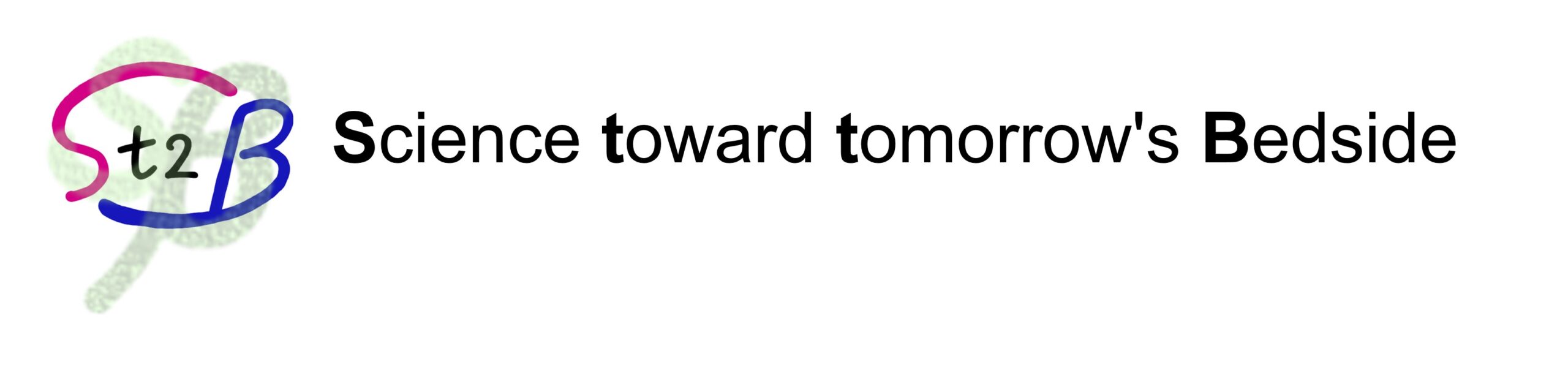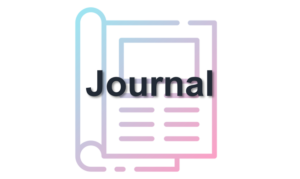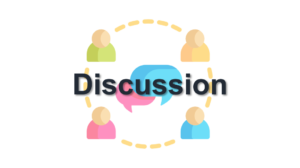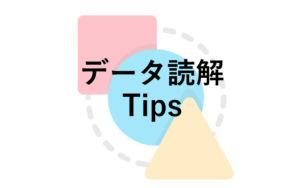pan-tumor
休眠細胞の目覚め:ウイルス感染とがんの再発の驚くべき関連が明らかに!
がん治療にとって、初回治療でいかに寛解に近い状態に持ち込めるか、と同時に、いかに再発を抑えるか、ということが完治(cure)の観点において重要なカギとなる。 この再発を抑えるための昨今の研究の方向性としては、大きく分けて […]
術前免疫療法の最適な効果判定/予後予測の方法は?:最近の肺がんのデータをもとに考える
肺がん治療において、サンドイッチICI(術前+術後ICI)療法の臨床導入が進む中、術前療法の適切な評価法および術後介入の必要性は、残された大きな課題だ。 今年のAACRでは、CheckMate-77T試験(術前Nivol […]
体内時計を制するものは、がん治療を制す!?:免疫療法のタイミングを考える
がん薬物療法の要である免疫療法を実施する際、投与タイミングはどこまで重要か? そもそも生体内には概日リズムが備わっている。Bmal1とClock遺伝子から作られるタンパク質(BMAL1とCLOCK)がヘテロ二量体を形成し […]
免疫チェックポイント阻害剤の効果と免疫環境:効果の持続性や併用のメリットに必要な条件は?
先日開催されたASCO-GI 2025での発表と同時に論文がリリースされたCM 8HW試験(André T et al. Lancet 2025)。今回は、MSI-H/dMMRの進行大腸がんに対するNivo+Ipi vs […]
術前療法 vs. 術後療法、臨床試験データを比較して大丈夫?
進行期がメインの対象であったIOやTKIの薬剤開発も、現在はより早期をターゲットにしたものに移行しつつある。 今回はその中でも周術期の治験を見るときの注意について考えてみたい。 術前療法における治験では、術前治療の前にラ […]
免疫チェックポイント阻害剤の効果を正しく評価し次治療を考えるために:RECIST評価の限界
免疫チェックポイント阻害剤(ICI)は、特徴的な効果発現パターンを持つことから、従来の化学療法や分子標的薬の効果判定に使われているRECISTによる評価では限界があることが以前から指摘されている。 この点に関してつい最近 […]
免疫チェックポイント阻害剤の投与はいつまで継続すべきか?(その2)
進行期固形がんに対する免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の最適な継続期間について、先日興味深い論文が報告された(Taieb J et al. J Immunother Cancer 2025)。 この話題は以前の記事で […]
放射線療法と免疫療法の併用療法:それぞれの効果を最大限に引き出すには?
以前の記事の中で、局所療法である放射線療法(RT)と全身療法である免疫療法(ICI)との併用の可能性について書いた。その時には、併用がいかに有望であるかについて自信満々に書いたわけだが、最近のデータを見ていると、そう単純 […]
治験の評価対象集団の選び方はそれで大丈夫?:Immortal-time biasの落とし穴
例えば、手術の有無による生存期間の比較を後ろ向きに解析する場合を考えてみる。このとき、単純に『非手術症例=手術歴なしの症例』、『手術症例=手術歴のある症例』と分類すると… 手術予定日までに何らかのイベント発生により脱落し […]